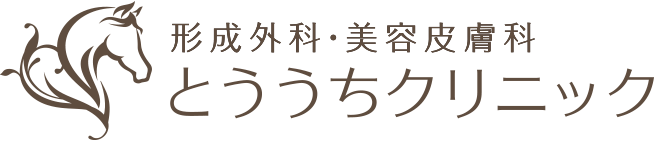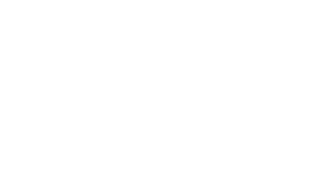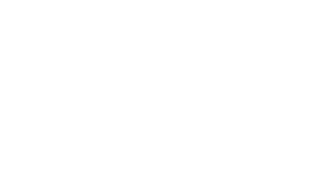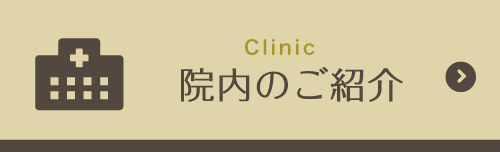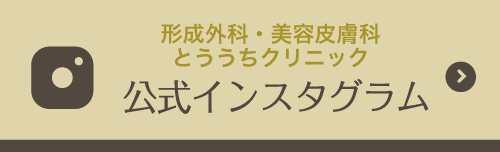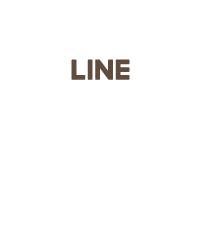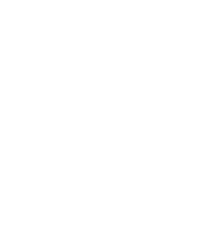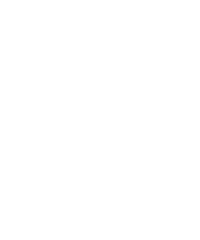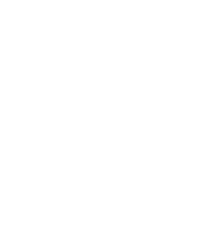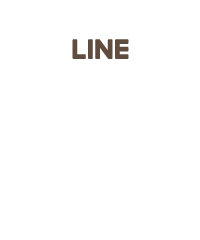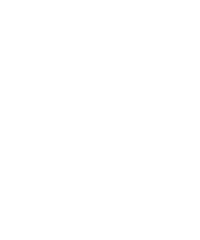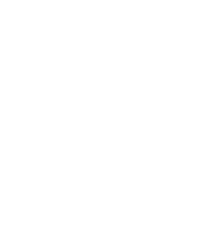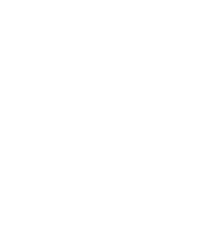粉瘤とは
粉瘤は、皮膚の中に袋(嚢腫)ができ、袋の内側から角質や皮脂が作られ続けて溜まる良性のしこりです。医学的には「表皮嚢腫(epidermal cyst)」などと呼ばれます。にきびや脂肪腫と紛らわしいことがありますが、性質も治療も異なります。
背中で大きくなりやすい理由
背中の粉瘤が他部位より大きく育ちやすいのには、次の要因が重なります。
袋(嚢腫壁)が“作り続ける”構造
袋の内面は角質を生み出す細胞で覆われており、放置しても自然に止まりません。出口(黒い点=開口部)が詰まると、内容物が抜けにくくなり、時間とともに確実に体積が増加します。背中は“気づきにくい”部位
鏡で見えにくく、痛みがない初期は放置されがち。受診までの期間が長引きやすい=その分大きくなる傾向があります。機械的刺激(摩擦・圧迫)
リュック・肩紐・衣類の縫い目、就寝時の体圧などの慢性的な摩擦が、開口部の詰まりや嚢腫壁の反応性肥厚を助長します。炎症の反復
内部に細菌が入り込んだり、内容物が皮下に漏れたりすると赤く腫れて痛む“炎症性粉瘤”になります。
炎症が一度おさまっても、袋は残るため再び内容物が溜まり、結果としてサイズアップしやすくなります。皮膚の張力が強い
背中は皮膚の張力(テンション)が強く、嚢腫が外側へ逃げにくいため、皮下で立体的に大きくなりやすい部位です。
放置で起こりうること
しこりの増大、衣類との摩擦による痛み・出血・悪臭
繰り返す炎症や自壊(破れて膿が出る)
炎症後の色素沈着や瘢痕(目立つ傷あと)
まれに背中全体に及ぶ蜂窩織炎などの強い炎症
※粉瘤それ自体は良性腫瘤ですが、自然に消えることは基本的にありません。
受診・治療の目安
次のような場合は、炎症が落ち着いているうちに(痛みや赤みが少ない時期に)ご相談ください。
直径1cm以上、あるいは月単位で増大している
繰り返し腫れる/痛む/臭い内容物が出る
衣類に当たって生活に支障が出る
にきびや脂肪腫か自己判断が難しい
診断:形成外科・美容皮膚科での見極め
視触診:中央の開口部(黒点)、弾性、可動性を確認
エコー検査(必要に応じて):内容物の貯留や嚢腫壁の連続性を評価
鑑別:脂肪腫、膿瘍、類表皮嚢腫以外の嚢胞性病変 など
※当院では悪性所見が疑われる場合、適切な画像検査や病理検査を検討します。
治療の基本方針
粉瘤の根治には「袋(嚢腫壁)」の完全摘出が必要です。内容物だけを押し出す・針で抜くなどの処置は再発の原因になります。
1. 根治手術(嚢腫摘出術)
炎症のない時期に、局所麻酔下で袋ごと摘出
背中の皮膚割線(テンションライン)に沿った切開と丁寧な縫合で、傷あとを最小化
サイズや位置により、紡錘形切除・くり抜き(パンチ)併用・小切開法を選択
2. 炎症期の対処(応急処置)
強い腫れ・痛み・発熱時は、切開排膿や抗菌薬で炎症をコントロール
炎症が落ち着いた後、改めて嚢腫摘出を行うと再発が少なく、傷あとも整えやすいです。
背中ならではの術後ケア
テーピング(皮膚の張力コントロール)を数週間継続
入浴・運動再開は創部の状態に合わせて指導
日焼け対策と保湿で色素沈着を予防
リュックや硬い縫い目が当たらない衣類選び、就寝時の体位工夫も有効
よくある質問
Q. 小さいうちは様子見でも良い?
A. 増大傾向や摩擦部位では早期摘出が理想です。小さいほど手術創が短く、ダウンタイム・再発率・費用面の負担が軽くなります。
Q. 炎症がある時にそのまま取れますか?
A. 強い炎症時の一括摘出は難度が上がり、傷あと・再発のリスクが増えます。多くはまず炎症コントロール→後日摘出が安全です。
Q. 自分でつぶすと早く治りますか?
A. 厳禁です。炎症悪化や細菌感染、色素沈着・大きな瘢痕の原因になります。
当院の特徴(例)
形成外科専門医による、部位特性(背中の張力)を考慮したデザイン切開と縫合
炎症期から根治手術、術後ケアまで一貫したフォロー
目立ちやすい背中の傷跡に対し、創閉鎖・テーピング指導・スキンケアを徹底
にきび・脂肪腫など類似疾患の正確な鑑別も実施
受診をご検討の方へ
しこりが大きくなる前、炎症のない時期のご相談がベストです。
「背中のしこり」「繰り返す腫れ」「においが気になる」など、気になる症状があれば早めにご予約ください。
まとめ:背中の粉瘤が大きくなる最大の理由は、袋が角質を作り続ける構造と、気づきにくさ・摩擦・炎症の反復です。根治には袋ごとの摘出が必要。適切なタイミングでの形成外科的手術と、背中特有のアフターケアが、再発と傷あとを最小限にする近道です。