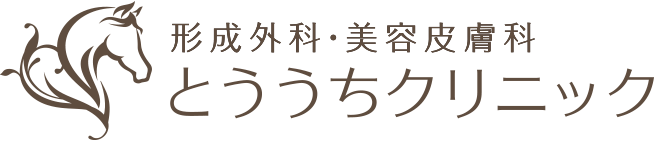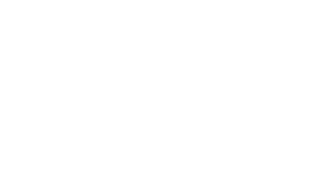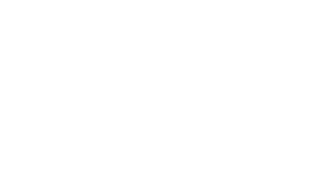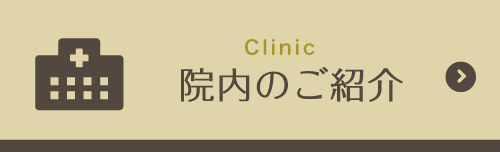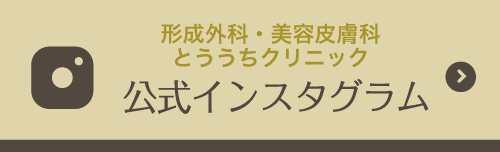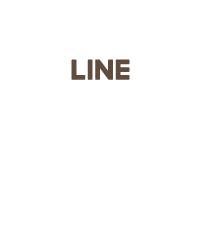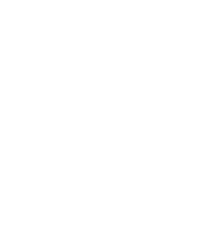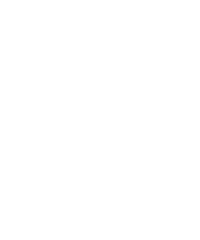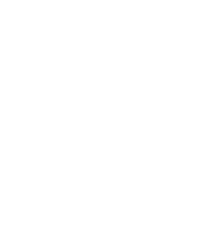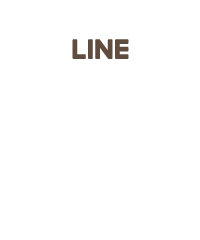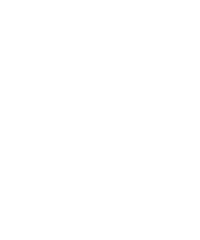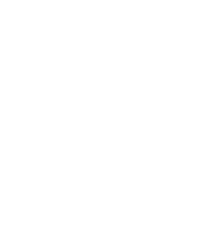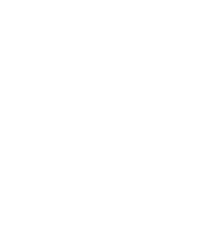粉瘤(ふんりゅう/表皮嚢腫)は、皮膚の下に袋(嚢胞)ができ、角質や皮脂がたまる良性の腫瘤です。表面に小さな黒点(開口部)があることも多く、炎症を起こすと赤く腫れて痛みや膿を伴います。
結論:自分で膿を押し出すのはNG。 一時的に膿が減っても袋の壁(嚢胞壁)が残るため再燃・再発しやすく、合併症のリスクも上がります。
自己処置(しぼる・針で刺す・切る)の主なリスク
感染拡大・蜂窩織炎:雑菌が入り、赤み・腫れ・発熱が増悪。抗菌薬や切開排膿が必要になることがあります。
膿瘍形成・瘻孔化:不完全な排膿で奥に膿の袋が広がり、皮膚にトンネル状の通り道(瘻孔)が残ることがあります。
出血・血腫・痛みの増強:強圧や誤った切開で出血し、腫れや疼痛が長引きます。
傷跡が目立つ・色素沈着:無理な圧出は皮膚損傷と炎症後色素沈着の原因に。特に顔は瘢痕が残りやすい部位です。
再発の反復:膿だけ出しても嚢胞壁が残る限り、においのある内容物やしこりが再形成されます。
誤診の見逃し:脂肪腫・粉瘤以外の腫瘤、稀な腫瘍や感染症を見落とすおそれ。
抗菌薬の自己判断使用:不適切な内服・塗布は耐性化や治療遅延につながります。
炎症が強いときの正しい対処
やってよいこと
清潔:泡でやさしく洗い、擦らない。
保護:ワセリンで薄く保護し、ガーゼや絆創膏で覆う。
冷却:清潔な保冷材で短時間クーリング(凍傷に注意)。
鎮痛:市販の鎮痛薬(例:アセトアミノフェン)※既往歴により使用可否は異なります。
やってはいけないこと
強く押す/針で刺す/カミソリ等で切る
過度の消毒(皮膚刺激・治癒遅延の原因)
入浴で長湯・激しい運動・飲酒(腫れが悪化)
自己判断での抗菌薬多用
すぐに受診を
発熱・急速な腫れ、強い痛み、糖尿病や免疫低下がある、顔面の腫れ、赤いスジが伸びる・悪臭が強い、妊娠中、乳幼児の病変 など。
医療機関での標準治療(当院の方針)
1)炎症期:まずは痛みと腫れを抑える
形成外科で切開排膿+創部洗浄・処置、必要に応じて抗菌薬。
無理に袋ごと切除しようとすると傷が大きくなるため、炎症が落ち着くまで待つのが原則です。
2)炎症が落ち着いた後:再発予防の根治治療
嚢胞壁を含めた摘出が再発防止のポイント。
部位・大きさにより
くり抜き法(へそ抜き法):小切開で内容物を除去し、嚢胞壁を丁寧に抜き取る低侵襲法
紡錘形切除:皮膚ごと袋を切除し縫合
いずれも局所麻酔。多くは日帰り手術で対応可能です。
医学的に適応があれば保険診療の対象(詳細は診察時にご案内)。
美容面の配慮(当院・美容皮膚科)
顔や露出部はデザイン切開・縫合で傷跡の目立ちにくさに配慮します。
術後の赤みや色素沈着には紫外線対策・テーピングを行って頂きます。
よくある質問
Q. においのある膿を出したら小さくなりました。治った?
A. 一時的に小さく見えても袋が残っている限り再発します。再燃前にご相談ください。
Q. 市販の軟膏で良くなりますか?
A. 炎症の軽減に限界があり、根治には嚢胞壁の摘出が必要です。自己判断の長期使用は避けましょう。
Q. 手術は痛い?傷は目立つ?
A. 局所麻酔で痛みは最小限。切開線の方向や縫合で目立ちにくい傷を目指しますが、部位・大きさで個人差があります。
当院受診の流れ
診察(状態評価・治療計画のご提案)
炎症期は処置・内服調整 → 再発予防の摘出は炎症鎮静後に実施
術後ケアと再発予防の生活アドバイス(洗浄・保護・紫外線対策 など)
注意事項
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としています。
実際の診断・治療は、症状の部位・大きさ・状態・既往歴などにより異なります。
気になる症状がある場合は、自己処置に頼らず、必ず医療機関へご相談ください。
眼瞼下垂、医療脱毛、シミ取り治療、たるみ治療をご検討の方は、豊中・千里中央にある「形成外科・美容皮膚科 とううちクリニック」へ是非お越しください
豊中・箕面・吹田の地域に密着したクリニック
茨木、高槻、池田、川西、大阪市内からもたくさんの患者様にご来院頂いています。
この記事は 形成外科・美容皮膚科 とううちクリニック 院長 當内竜馬(日本形成外科専門医)が監修しています。